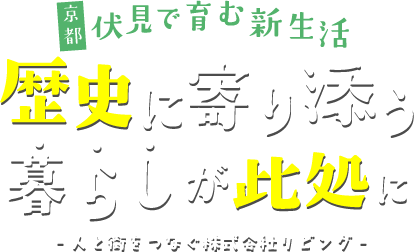ぱんくずリスト
コラム&地域情報 詳細

画像引用元:Wikipedia
京都六地蔵の一つ「大善寺」の見どころとは?
はじめに
京都伏見に「六地蔵」と呼ばれ、参拝客に親しまれている寺院があります。六地蔵と呼ばれる由来は、当初6体の地蔵尊が安置されていたため。現在は、1体のみ大善寺に安置されています。
残りの地蔵尊は、同じ伏見にある5箇所の寺院に納められており、6つの寺院を巡る六地蔵めぐりが有名です。無病息災・家内安全を祈願する多くの参拝客が地蔵盆に訪れます。
今回は、京都伏見にある六地蔵と呼ばれる「大善寺」の見どころをご紹介します。
大善寺とは?
京都伏見にある浄土宗の寺院、通称「六地蔵」。
705年藤原鎌足の子、定恵が創建した法雲寺が起源とされています。平安時代前期の852年に、円珍が天台宗に改宗しました。その後、兵火によって焼失します。1561年に浄土宗寺院として再興し、名称も大善寺に改められました。
寺院内の地蔵堂に安置されているのは、朝廷の役人であった小野篁が作ったとされる地蔵菩薩立像(重要文化財)。六地蔵めぐりの名所となっており、毎年8月22日・23日の地蔵盆には参拝客でにぎわいます。
大善寺が「六地蔵」と呼ばれる理由
6体の地蔵尊が大善寺に祀られていたのが由来とされ、現在でも「六地蔵」と呼ばれています。
平安時代、朝廷の役人であった小野篁が熱病を患い、仮死状態に。冥土に行き、生身の地蔵尊を拝んだことで蘇ります。蘇った小野篁は、1本の桜の木から6体の地蔵尊を掘り出し、大善寺に納めました。
その後、都へ通じる六ヶ所の主要街道に、平清盛が地蔵尊を安置させたとのこと。現在、地蔵尊1体が大善寺に、残りの5体は街道口にある5箇所の寺院に安置されています。
大善寺のご利益
厄病退散や福徳招来のご利益があるとされている大善寺。六つの地蔵尊が安置されている6箇所の寺院をめぐり、無病息災・家内安全を祈願します。
各寺院には、御旗と呼ばれる6色のお札が用意されています。赤・青・白・黄・緑・紫の6枚をまとめて玄関につるしておくのです。
六地蔵を全てめぐると総距離は、約35km。徒歩で巡礼する人は珍しいですが、平坦な道が多く、ところどころにサイクリングロードもあるので、運動ついでに参拝するのもおすすめです。道沿いには、渡月橋で有名な桂川や太秦映画村などがあり、風を感じながら景色も楽しめるでしょう。
大善寺へのアクセス
大善寺へのアクセスは下記の通りです。
住所:京都市伏見区桃山町西町24
拝観時間: 9:00~16:00
拝観料:無料
駐車場:あり
アクセス:
・京阪「 六地蔵駅」から 徒歩6分
・JR・地下鉄「六地蔵駅」から 徒歩10分
境内には無料の駐車場(約10台)がありますので、お車でもアクセスしやすいです。
フッター
京都府知事 (3) 第13382号
Copyright ©リビング All Rights Reserved.