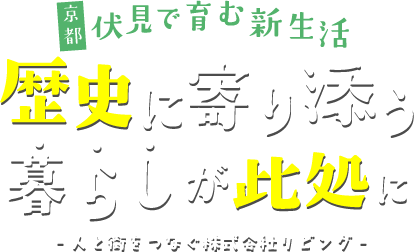ぱんくずリスト
コラム&地域情報 詳細

伏見のランドマーク!三栖閘門資料館の見どころをチェック!
はじめに
三栖閘門とは、京都伏見にある宇治川と濠川の合流点に設けられている閘門であり、伏見の街を水害から守ために建設されたものです。
現在は船の運行はなく、三栖閘門資料館が解説され、伏見の宇治川の歴史を伝えています。
伏見観光で有名な十石船のルートにも入っており、資料館の見学も含まれています。
今回は、伏見のランドマークである三栖閘門資料館の見どころについてご紹介します。
三栖閘門資料館とは
三栖閘門資料館とは、京都伏見にある宇治川と濠川の合流点に設けられている閘門の歴史を知ることができる場所です。
元々は操作室だったものを改装して、資料館として利用されています。
資料館の中では、模型を使って三栖閘門の仕組みを解説したり、江戸時代の伏見港と伏見の町が展示されていたり、伏見の様々な歴史について知ることができます。
三栖閘門は大阪と京都を結ぶ淀川の舟運の拠点
三栖閘門は伏見港と宇治川を結ぶ施設として、1929(昭和4)年に建設されました。
宇治川と濠川の合流点に位置していますが、2つの運河は水位が異なるため、伏見への水害を守る目的もあったのです。
三栖閘門は水位の違う2つの川の水位を調整して、船を通すための重要な施設でした。
江戸時代には十五石舟、明治時代には蒸気船が運行していましたが、道路や鉄道の発達に伴い、1962(昭和37)年に役割を終え、現在は観光地の一つとなっています。
三栖閘門はパナマ運河と同じ仕組み
三栖閘門は、パナマ運河と同じ仕組みで作られています。
かつてパナマ運河の建設にも日本人が関わっており、設計図を取り寄せることができたと言われています。
大まかな仕組みは下記の通りです。
2つの水位が異なる川の間に閘室があり、閘室で水位を調整してから水門を開けることで、水位の違いの影響を受けることなく通過できるというもの。
水位が低い方から渡る場合は、閘室に注水することで水位を合わせます。
逆の場合は、排水して水位を合わせてから水門を開けて通過することで、同じ水位のまま通過することが可能になります。
2003年には伏見のシンボルとして再生
道路や鉄道の発達、そして宇治川上流に天々瀬ダムの完成により役目を終えた三栖閘門。
40年の年月を経て三栖閘門の修復と併せて周辺の公園が整備され、「三栖閘門と伏見みなと広場」として2003年にリニューアルオープンしました。
閘門の開閉の扉室の塔の屋上からは、宇治川や伏見の街が展望できる観光スポットになっています。
公園内には四季折々の樹木が植えられており、季節問わず楽しめる場所として、観光客からも地元住民からも愛されています。
三栖閘門資料館へのアクセス
三栖閘門資料館は、京阪中書島駅から徒歩10分の場所にあります。
料金は無料ですが、月曜日と年末年始が休館日となっていますので注意してください。
また、十石舟のルートにも入っているので、伏見観光をお考え方は十石舟で訪れるのもおすすめです。
フッター
京都府知事 (3) 第13382号
Copyright ©リビング All Rights Reserved.