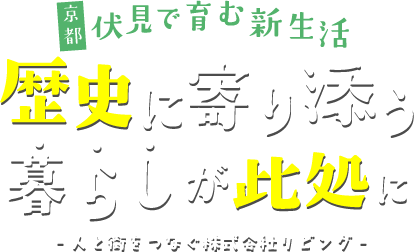ぱんくずリスト
コラム&地域情報 詳細

引用元:京都観光オフィシャルナビ
幕末の歴史を感じる京都伏見スポット「伏見奉行所跡」とは?
はじめに
古くからの歴史を感じる観光スポットが多い京都伏見ですが、かつては伏見を統治する拠点として「伏見奉行所」がありました。
鳥羽伏見の戦いで建物は炎上し、現在は石碑と案内板のみが残っている状態です。
幕末の歴史を後世に静かに語り続ける石碑には、歴史を感じる趣深い雰囲気を感じます。
今回は、幕末の歴史を感じる京都伏見スポット「伏見奉行所跡」についてお伝えします。
伏見奉行所跡の歴史
伏見奉行所の設置は徳川幕府の時代まで遡ります。
平安時代から貴族の別荘地だった伏見ですが、豊臣秀吉の伏見城築城をきっかけに城下町として発展しました。
商業と交通の一大拠点にまで発展し、伏見の町を監視するために徳川幕府は寛永元年(1624年)に伏見奉行所を設置。
1666年には水野忠貞が初代伏見奉行に任じられ、その後、廃止を経て新撰組が入り、鳥羽伏見の戦いで消失します。
歴史に残る鳥羽伏見の戦いとは?
鳥羽伏見の戦いによって新撰組や会津藩が立て篭もったことで知られる「伏見奉行所」ですが、御香宮神社に本陣をおいた薩摩連合軍による攻撃で炎上してしまいます。
この鳥羽伏見の戦いは、新政府軍と旧幕府軍の戦いです。
1867年10月に幕府は大政奉還を決め、王政復興の大号令を発令。
徳川幕府の権力を維持したまま新政府に残ろうとした徳川慶喜でしたが、岩倉具視らの策略によって新政府メンバーから除外されてしまいます。
徳川慶喜を新政府に加えるための条件として、内大臣の官位を辞官、幕府の所領を朝廷に返上するなどの条件を提示。
この条件を飲めない徳川慶喜は、朝廷工作を開始し上手く進めることができたが、江戸の薩摩藩邸が旧幕府軍に襲われ、戦争の口実を作る形となってしまいました。
この暴動をきっかけに、徳川慶喜は京を攻め、この戦争が鳥羽伏見の戦いになります。
その後は、旧幕府軍が敗北し、江戸城を無血開城し、会津戦争、五稜郭の戦いが繰り広げられ、鳥羽・伏見の戦いから始まった戊辰戦争が終わりを迎えます。
鳥羽伏見の戦いで建物は炎上し現在は石碑のみが残る
新政府と旧幕府の全面戦争によって、伏見奉行所の建物は炎上し、現在は石碑のみが残ります。
かつては、北方に奉公屋敷があり、道路を隔てた西方と奉行所南方に与力・同心などの組屋敷がありました。
伏見奉行所跡へのアクセス
伏見奉行所跡は、京都市伏見区伏見区西奉行町の桃陵団地内にあります。
伏見桃山駅から徒歩5分の場所に位置しており、団地の一角にひっそりと佇み、静かな古き良き京都の歴史を感じられるでしょう。
フッター
京都府知事 (3) 第13382号
Copyright ©リビング All Rights Reserved.