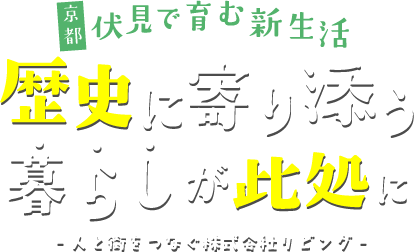ぱんくずリスト
コラム&地域情報 詳細

※画像はイメージです
桜の名所として人気の「墨染寺」の見どころと伝説とは?
はじめに
京都伏見にある桜の名所で有名な墨染寺ですが、別名「桜寺」とも呼ばれています。
平安時代から続く伝説が、「墨染」の地名の由来となり、今でも引き継がれているのです。
境内には「墨染」の地名の由来となった「墨染桜」があることでも知られています。
現在は、3代目、4代目の墨染桜が育っているので、桜の時期にぜひお立ち寄りください。
今回は、京都伏見の桜の名所である「墨染寺」の見どころについてご紹介します。
別名「桜寺」とも呼ばれる墨染寺とは?
「墨染寺」は桜の名所でも知られており、別名「桜寺」と呼ばれています。
平安時代の874年の清和天皇の勅願により創建され、その後荒廃するも安土桃山時代に豊臣秀吉が土地を寄進して復興。
江戸時代に現在の場所へ移され、お寺の「墨染」という地名の由来にもなっているのです。
こじんまりした小さな寺院ですが、桜の季節には境内を埋め尽くすほどの光景が観られます。
墨染め色に咲く「墨染桜」にまつわる伝説とは?
寺院の由来や地名にもなっている「墨染」ですが、境内に咲くある桜が言葉のルーツとなっているのです。
墨染寺は、京都では珍しい薄墨色の桜が見れることでも有名。
この「墨染桜」には、語り継がれてきた伝説があるのです。
平安時代の太政大臣・藤原基経が亡くなった際に友人である上野岑雄(かみつけのみねお)が、このような歌を詠みました。
「深草の野辺の桜し 心あらば 今年ばかりは墨染に咲け」
悲しみを込めて詠んだ「桜に心があるなら、今年は墨染に咲いて欲しい」との思いが通じたのか、墨染め色の桜が咲いたとの言い伝えがあるのです。
墨染桜は3代目、4代目と順調に成長し、伝説と共に現代にも引き継がれています。
京都伏見の隠れた桜の名所
墨染寺は京都の街中にある隠れた桜の名所です。
桜の名所はたくさんありますが、少し変わった穴場スポットをお探しの方や新しい桜の名所に行きたい方におすすめです。
特に桜の季節にはソメイヨシノや墨染桜が楽しめるので、京都観光にもぴったりでしょう。
桜の観光時期は、4月上旬から中旬頃がおすすめです。
墨染桜は他の桜よりも少し遅れて開花するため、4月の下旬ごろが見頃になります。
墨染寺へのアクセス
墨染寺の住所
〒612-0051 京都府京都市伏見区墨染町741
電車でアクセスする場合
・京阪電車「墨染」駅から徒歩3分
・JR奈良線「藤森」駅から徒歩14分
・近鉄京都線「伏見」駅から徒歩12分
拝観時間は8:00〜17:00となっており、境内の見学は無料です。
フッター
京都府知事 (3) 第13382号
Copyright ©リビング All Rights Reserved.