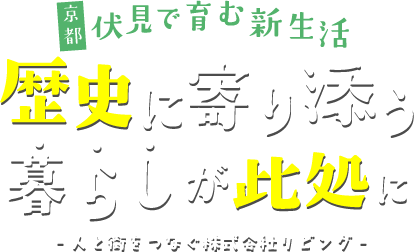ぱんくずリスト
コラム&地域情報 詳細

※画像はイメージです
油をかけると願い事が叶う!?西岸寺の油懸地蔵と呼ばれる由来とは?
はじめに
歴史の残る京都伏見には様々なパワースポットや観光名所が充実。
そんな数多くのスポットの一つに「油懸地蔵(あぶらかけじぞう)」と呼ばれる場所があります。
場所は、京都伏見に位置する「西岸寺」。
ここでは、地蔵に油をかけて祈願すれば願いが叶うと言われているのです。
今回は、京都伏見の観光スポットの一つである油懸地蔵の由来や歴史についてご紹介します。
油懸地蔵と呼ばれる由来
京都伏見にある西岸寺は、通称油懸地蔵の名で親しまれてきました。
油懸地蔵の由来は、油をかけて祈願すれば願いが叶うとの言い伝えから。
この言い伝えの通り、地蔵尊が黒光していることも見どころの一つ。
寺伝によれば、むかし大山崎(乙訓郡)の油商人が油桶を背負って伏見を歩いていたところ、西岸寺の前を差し掛かった時に転んでしまい、油桶の油が流れ出てしまいました。
当時は油は高級なものであり、商人は途方に暮れていましたが、気を取り直し残ったわずかな油を地蔵さまに掛けて帰りました。
すると、この商人は商売が繁盛しまもなく大金持ちになったと言うことです。
以後、地蔵尊に油をかけて祈願すれば願いが叶うと言われ、人々から信仰を集めているのです。
安土桃山時代に創建されたが鳥羽・伏見の戦いで類焼
油懸地蔵で有名な京都伏見の西岸寺ですが、創建されたのは安土桃山時代と言われています。
1590年に僧の岸誉雲海によって創建されましたが、幕末の1868年の鳥羽・伏見の戦いで本堂は類焼しました。
その後、1894年(明治27年)に地蔵堂が再建、1978年に現在の地蔵堂が再建され、本堂は2008年に再建されたものになります。
本堂に祀られている地蔵尊は鎌倉時代に作られたと予測されますが、黒光するほどに表面に油が厚く積っており、刻まれている文字も読み取れないほどになっています。
油懸地蔵は京都市内に3カ所ある
油をかけて祈願すれば願いが叶うと言われている「油懸地蔵」は、伏見以外にも3カ所あります。
①京都伏見区油掛街(西岸寺)
②左京区嵯峨天龍寺油掛町
③右京区梅津中村町(長福寺)
嵯峨の油懸地蔵は、ここを通る商人は必ず油を地蔵にかけて祈願をしていたとの言い伝えがあります。
現在も地域の人々によって大切に管理されており、多くの参拝者が訪れる場所でもあります。
長福寺にも油懸地蔵が安置されていますが、現在は堂内に安置されており、油をかけることはできません。
京都伏見にある西岸寺へのアクセス
京都伏見にある西岸寺へのアクセスは、下記の通りです。
・京阪「中書島」駅下車、徒歩約10分
・市バス「京阪」下車、徒歩約3分
電車で訪れる場合は京阪電車「中書島」からアクセスすると最短ルートになります。
【西岸寺】
・住所:京都市伏見区下油掛町898
・営業時間:9:00〜16:00
・定休日:無休
フッター
京都府知事 (3) 第13382号
Copyright ©リビング All Rights Reserved.